お知らせ
【季節いろいろ】暦
2010/06/20
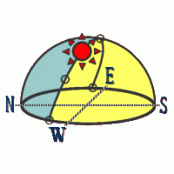
日本は四季のある国です。
季節それぞれにはいろんな風習や特徴がたくさんあります。
そんな四季折々の行事などに、子供さんたちにもできる限りふれてほしいと思います!
そしてまず今回はそんな季節を表す<暦>の説明からしたいと思います。
<二十四節気(にじゅうしせっき)>
一年を二十四等分に区切って名前をつけ季節を表したもの。太陰太陽暦において月名を決定し、季節とのずれを調整するための指標として使われる。現在の暦にあわせると毎年少しずつ日付が違っている。
<五節句(ごせっく)>
もとは中国から伝えられた風習で、伝統的な年中行事を行う季節の節目となる日で、日本の文化・風習のこと。江戸時代に幕府が公的な祝日として定めた日。
<雑節(ざっせつ)>
季節の移り変わりをより適確に掴むために設けられた、二十四節気を補助する日本独特の暦日のこと。季節を重視した内容で農作業の指標になる。
<旧暦(きゅうれき)>
現在使われている太陽暦以前の太陰太陽暦のことで、今の暦に比べて約一ヶ月ほど遅い。
文字で説明すると少し難しいですが、前回【季節いろいろ】でご紹介したこいのぼりの端午の節句が<五節句>、八十八夜・入梅が雑節にあたります。やはりこんな暦の行事に関わってますよね!ですからその暦の由来もすこ~し頭に置いておいて頂ければ、行事をするにも色んな意味を感じてもらえると思います。
【季節いろいろ】のコーナーではこれからもいろんな季節の成立ち・行事などをお知らせしていきたいと思います♪